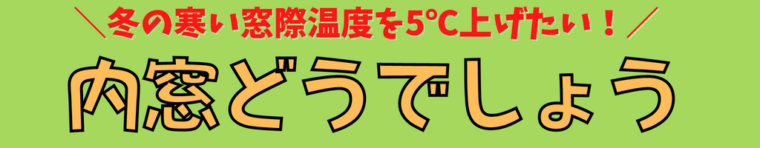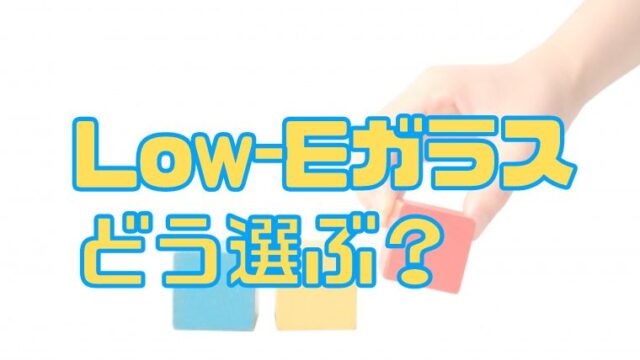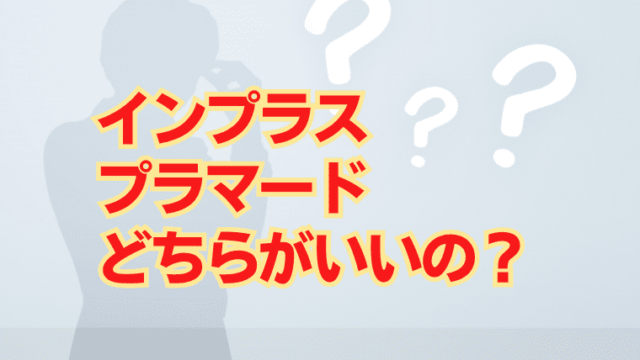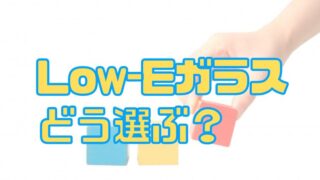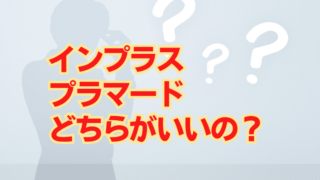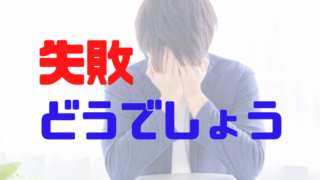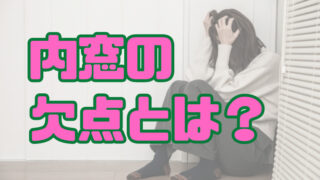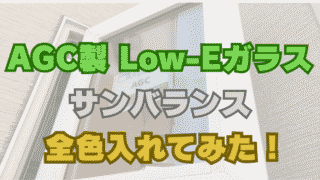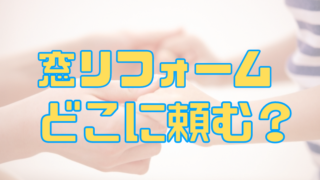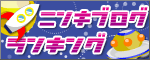後悔しない二重窓の選び方とは?特徴やポイントをわかりやすく解説!
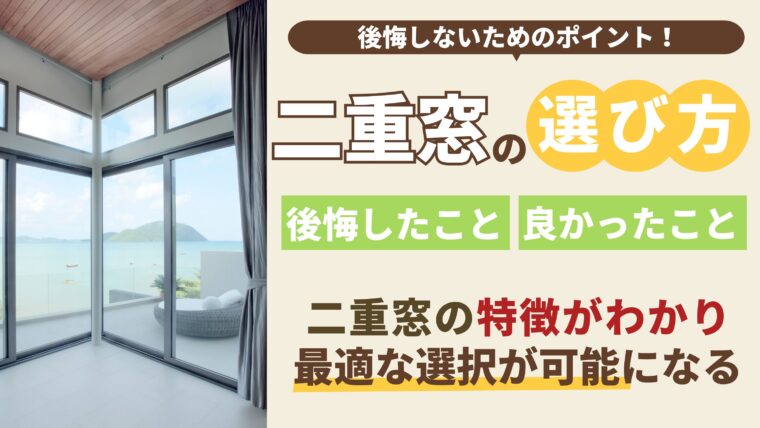
二重窓の選び方や注意点を知りたい人は多くいます。この記事では、二重窓にして後悔したことや良かったこと、後悔しないための選び方のポイントなどを解説します。
記事を読めば、二重窓の特徴がわかり、自分に合った最適な選択が可能です。二重窓を選ぶ際は、メリットとデメリットの理解が重要です。
設置目的を明確にして信頼できる専門業者に依頼すると、後悔のない適切な二重窓を選べます。
二重窓にして後悔したこと

二重窓の設置には多くのメリットがある一方で、後悔する点もあります。二重窓にして後悔しがちなことは、以下のとおりです。
- 掃除や開閉が面倒になった
- 結露が発生してしまった
- 価格を重視しすぎた
- 部分的にしか設置しなかった
- DIYで取り付けて失敗した
- 部屋が狭く感じるようになった
- 防音効果が期待外れだった
掃除や開閉が面倒になった
二重窓を設置すると、窓の構造が複雑になり、掃除や開閉が面倒になる場合があります。二重窓の掃除を怠ると、窓の間にホコリや虫が入り込みやすくなります。
2回開けるのが面倒になるので、窓の開閉頻度が減り、換気不足になりやすいこともあります。
開閉操作が複雑になるため、子どもや高齢者にとって窓の操作が困難になる点にも注意が必要です。問題を事前に理解し、対策を考えましょう。
清掃しやすい構造の二重窓や、開閉操作が簡単な製品の選択がおすすめです。
結露が発生してしまった
二重窓は通常、結露を減少させる目的で設置されますが、条件によっては結露が発生することもあります。見た目が悪いだけでなく、カビやサビの原因にもなるため注意が必要です。
結露が発生する主な理由は、室内外の温度差と湿度のバランスにあります。換気不足も結露を助長する重要な要因の一つです。
二重窓の種類や設置方法によって、結露の程度は異なりますが、基本的には室内の暖かく湿った空気が冷たい窓面に触れることで冷やされ、空気中の水蒸気が液体化して窓に付着します。
結露を放置すると、木枠の腐食や壁紙の劣化につながる可能性があるため、早めに対策しましょう。除湿器の使用が効果的です。
定期的な換気など、室内の湿度を適切に保つ工夫も重要です。結露防止フィルムや断熱シートを窓に設置すると、結露の発生を抑制できます。
価格を重視しすぎた

安さだけを追求すると、期待していた効果が得られない場合があります。発生する可能性がある問題は以下のとおりです。
- 断熱性能や防音性能が低い
- 低品質な部材が使われている
- 長期的なメンテナンス費用がかさむ
- 環境に適さない製品である
- デザインや機能性が劣る
初期費用を抑えるあまり、耐久性の低い製品を選んでしまい、数年後に交換が必要になるケースも見られます。価格は重要な要素ですが、品質や性能、耐久性なども考慮した選択が大切です。
部分的にしか設置しなかった
すべての窓に設置しないと、断熱効果が限定的になってしまいます。一部の部屋だけが快適な温度になり、他の部屋との差を感じるため、家全体の快適性が損なわれる傾向です。
投資対効果も低くなります。期待していた効果が得られず、満足度が下がる可能性があるため注意が必要です。
見た目のバランスも悪くなる可能性があります。一部の窓だけが二重窓になると、外観や内装の統一感が損なわれます。
将来的に全窓に設置する場合、コストが増加する点にも注意が必要です。最初からすべての窓に設置する方が、長期的にはコスト効率が良くなるのでおすすめです。
DIYで取り付けて失敗した
二重窓の取り付けには専門的な知識や技術が必要で、DIYでは失敗する恐れがあります。失敗例は以下のとおりです。
- 窓枠幅が足りず、ふかし枠の必要性を見落とした
- 窓枠との隙間を埋められず、隙間風が入った
- 窓枠の劣化に気づかず、歪みで窓が入らなかった
正確な採寸ができず、サイズが合わない二重窓を取り付けてしまう場合もあります。適切な工具や技術がなく、窓枠や壁を傷つけるケースもあります。
断熱効果が得られなかったり、開閉がスムーズにできなかったり、結露が発生したりするケースもあるのが現状です。安全面でのリスクも無視できません。
取り付けが不適切な場合、窓の落下や怪我の危険性が高まります。
部屋が狭く感じるようになった

二重窓にしたことによって、部屋が狭くなったように感じられる場合があります。窓枠が太くなり開口部が小さくなるからです。
内側に窓が追加されることで室内スペースが減少し、窓の開閉には内窓と外窓の両方を操作する必要があるため、手間が増えます。
カーテンやブラインドの設置位置が変わって圧迫感が増したり、窓際に家具を置くスペースが制限されたりするのも原因です。
室内からの景色が狭くなったように感じたり、採光量が減少して部屋が暗く感じたりする可能性もあります。
問題を避けるために、設置前に部屋のレイアウトや採光について十分に検討しましょう。窓枠の太さや開口部の大きさにも注意し、部屋の広さを損なわないよう慎重に選択してください。
防音効果が期待外れだった
防音性能が製品によって大きく異なるため、選択を誤ると十分な効果が得られません。高価格の製品でも、満足のいく防音効果が得られるとは限らない点に注意しましょう。
壁や床、天井や換気口など、窓以外の経路からも音が伝わる可能性があります。
防音効果の評価は主観的で個人差があるため、期待値と実際の効果にギャップが生じる傾向です。特定の周波数の音に対しては、効果が低い場合もあります。
設置場所や環境によっても効果が変わるので、事前の調査や専門家のアドバイスが重要です。
防音効果と換気のバランスも難しく、両立させるには工夫が必要になります。
二重窓にして良かったこと

二重窓にして良かったこととして、以下の点を解説します。
- 断熱性能で光熱費を削減できた
- 防音性能が高まった
- 防犯対策になった
断熱性能で光熱費を削減できた
二重窓で断熱性能が高まると、1年を通して冷暖房の使用頻度や設定温度を抑えられ、光熱費の大幅な削減に効果的です。
冬場は、室内の暖かい空気が外に逃げるのを防ぎ、暖房効率を高めます。暖房の設定温度を控えめにしても快適に過ごせるため、暖房費の節約が可能です。
夏場は、外からの熱気の侵入を遮断し、冷房効率を向上させられます。設定温度を上げても涼しく感じられるため、冷房費の削減が期待できます。光熱費の削減は、CO2排出量の削減にもつながるため、環境負荷の低減も実現可能です。
防音性能が高まった

外部からの騒音を効果的に遮断することで、室内の静かな環境を実現できます。交通騒音や工事音などの外部騒音の侵入を軽減し、会話や音楽などの外部への漏れを抑制する効果があります。
静かな睡眠環境の確保や、集中力を要する作業や勉強に適した環境の実現も可能です。
一般的に騒音レベルを10〜15デシベル程度低減させられます。高周波数帯域の音に対して効果的です。ガラスの厚さや種類を工夫すると、防音効果を高められます。
ガラスの厚さや空気層の幅によっては、低周波数帯域の音に対しても一定の効果を発揮します。
防犯対策になった
二重窓のガラスは通常の窓に比べて割れにくく、窓全体の強度も増すため、外部からの不正侵入を防ぐのに効果的です。具体的には、以下の防犯上のメリットがあります。
二重窓は防犯対策として一定の効果があります。二重窓は2枚のガラスがあるため、侵入者が両方のガラスを破る必要があり、侵入に時間がかかることから不正侵入を抑止する効果があります。
さらに防犯性能を高めたい場合は、防犯ガラスや防犯フィルムなどの専用の防犯製品を使用することが効果的です。
- 侵入に時間がかかり、侵入を困難にする
- 物理的な障壁が増えるため安全性が向上する
- 防犯フィルムとの併用で効果が高まる
- 防音効果により外部の騒音を軽減する
二重窓の二重構造により、ガラス破りなどの物理的な侵入手口が通用しにくくなるのも特徴です。必要に応じて防犯センサーなどの安全対策を追加すると、より高いセキュリティを確保できます。
後悔しないための二重窓選びのポイント
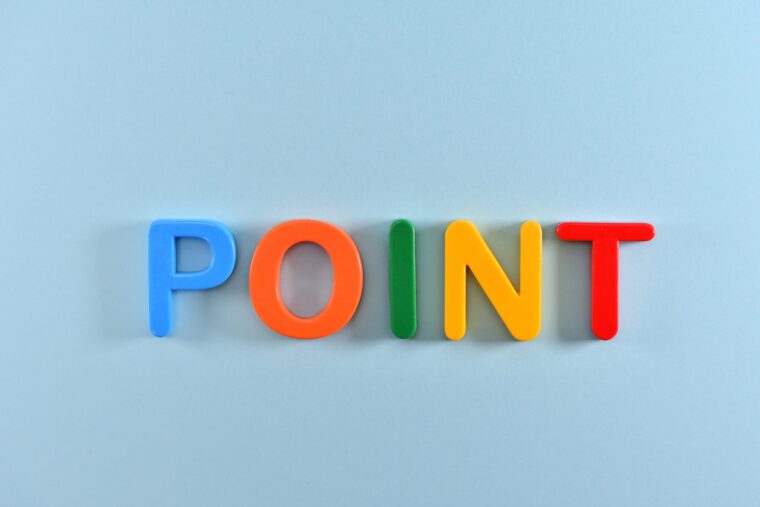
後悔しないための二重窓選びのポイントは以下のとおりです。
- 正しくデメリットを理解する
- 優先順位を決めて製品を選ぶ
- 設置目的を明確にする
- 補助金や助成金を活用する
- 信頼できる専門業者に依頼する
正しくデメリットを理解する
期待と現実のギャップを最小限に抑えるために、二重窓のデメリットを正しく理解しましょう。二重窓は窓が二重になるため、掃除や開閉の手間が増える場合があります。
設置状況によっては、結露が発生する可能性も否定できません。一般的な窓に比べて初期費用が高額になる傾向があります。
部屋全体ではなく一部分にのみ設置した場合、断熱効果が十分に発揮されない傾向です。DIYでの施工は、失敗のリスクや性能低下を招く恐れがあります。
内窓の設置により、部屋が狭く感じられる場合もあります。防音効果を高めますが、完全に音を遮断できるわけではありません。
優先順位を決めて製品を選ぶ
二重窓を選ぶ際は、断熱性能や防音性能、予算、デザイン、耐久性などの項目から、優先度の高い項目を選んでください。
寝室なら防音性能を、リビングなら断熱性能を重視するなど、使用する場所によって求められる機能が異なります。
メーカーの評判や保証内容や、窓の開閉方式や操作性、既存の窓枠との相性、省エネ性能や環境への配慮なども考慮します。将来的な修理や部品交換の可能性も考えておくと安心です。
設置目的を明確にする

二重窓の設置目的を明確にすると、自分のニーズに合った適切な製品を選べます。二重窓の主な設置目的は以下のとおりです。
- 断熱性能の向上
- 防音効果の改善
- 光熱費の削減
- 防犯対策の強化
- 結露防止
寒さ対策が主な目的であれば断熱性能の高い製品を、騒音対策が目的であれば防音効果の高い製品を選びましょう。複数の目的がある場合は、優先順位をつけて検討します。
補助金や助成金を活用する
国や自治体、各メーカーが提供するさまざまな支援制度があるので、上手に利用しましょう。具体的には、以下の制度があります。
- 国や自治体の補助金制度
- 先進的窓リノベ事業
- 子育てグリーン支援事業
- 各メーカーのキャンペーンや割引
制度を利用するには、申請期限や条件、必要書類などの事前確認が大切です。申請手続きの流れを把握し、必要な準備を整えると、スムーズに補助金や助成金を受け取れます。
信頼できる専門業者に依頼する
適切な業者を選ぶと、高品質な施工と長期的な満足度を得られます。経験豊富で評判の良い業者を探しましょう。複数の業者から見積もりを取得し、比較検討するのがおすすめです。
見積もりでは、施工実績や資格、保証内容をしっかりと確認してください。顧客評価や口コミの評判も注目すべきポイントです。
業者を選んだら、現場調査と詳細な打ち合わせをします。契約内容や工事スケジュールを明確にし、疑問点や要望は遠慮なく伝えましょう。
施工中も随時コミュニケーションを取り、業者の提案や助言に耳を傾けてください。施工後の点検や調整を依頼し、長期的な性能維持を図るのがおすすめです。
後悔すると言われる二重窓に関するよくある質問

二重窓に関するよくある質問は以下のとおりです。
- 設置にはどれくらいの時間がかかる?
- DIYで設置する際の注意点は?
- 浴室の窓も二重にできる?
- 補助金はどこで調べられる?
設置にはどれくらいの時間がかかる?
二重窓の設置工事自体は、通常は窓1か所あたり1時間程度で完了します。複数箇所を同時に施工する場合では、半日~1日程度かかるのが一般的です。事前の採寸や準備作業を含めても、1~2週間以内で完了します。
しかし、補助金などで注文が殺到する時期の場合、3カ月ほどかかる場合もあるので余裕を持って依頼しましょう。専門業者に依頼すると、経験や効率的な作業により、設置時間を短縮できる可能性があります。設置時間に影響を与える要素は以下のとおりです。
- 窓の数と大きさ
- 建物の構造や特性
- 作業の難易度
- 天候条件
- 設置時期
DIYで設置する際の注意点は?
DIYで二重窓を設置する際は、正確な採寸が重要です。窓枠のサイズを間違えると、隙間ができたり取り付けられなかったりする可能性があります。
適切な工具と材料の準備も大切です。専用の工具や高品質な材料を使用すると、作業がスムーズに進み、仕上がりも良くなります。
作業中のケガを防ぐため、保護具を着用し、安全な環境で作業してください。作業手順の確認と理解も重要です。手順を間違えると、取り付けに失敗する可能性があります。気密性と水密性の確保にも注意が必要です。隙間があると、断熱効果が低下したり雨水が侵入したりする恐れがあるためです。
既存の窓枠に悪影響を与えないよう、慎重に作業を進める必要があります。結露が発生しないよう、適切に対策をしましょう。
窓の性能を最大限に引き出すためには、内窓と外窓の間に適切な空気層を確保し、気密性を高めてください。窓の重量に耐えられる構造になっているかも、事前に確認しておくべきポイントです。
インパクトドライバー等の使用により、ご近所にある程度工事の騒音が伝わりますので配慮が必要となります。
浴室の窓も二重にできる?

浴室の窓も二重窓化が可能です。結露対策や断熱性向上に効果的で、防音効果も期待できます。
専用の浴室用二重窓製品があり、防水性や耐湿性に優れた素材を使用しています。既存の窓枠に取り付けるタイプが多いのも特徴です。取り付け工事は専門業者に依頼するのが安全です。
通常の二重窓より費用が高めになる傾向がある点に注意しましょう。浴室の環境に適した製品選びも重要です。
補助金はどこで調べられる?
補助金の主な情報源は、各自治体のホームページや国・都道府県の補助金サイトです。最新の補助金情報や申請方法を確認できます。
国土交通省や環境省の公式サイト、お住まいの地域の自治体窓口で確認が可能です。身近な相談窓口は以下のとおりです。
- 各自治体の住宅課や環境課などの担当部署
- 国の補助金事務局
- 地元の工務店や建築会社
- エネルギー事業者の相談窓口
窓口では、専門家から直接アドバイスを受けられるので、自分の状況に合った補助金を見つけやすくなります。不動産業者や金融機関の住宅ローン相談窓口も、補助金情報を得るのに役立つ場所です。
まとめ

二重窓の設置には、さまざまなメリットとデメリットがあります。断熱性や防音性の向上や、光熱費の削減、防犯対策の強化などがメリットです。一方で、掃除や開閉の手間、結露の発生、価格の高さなど、注意すべき点もあります。
後悔しないために、デメリットを正しく理解し、優先順位を決めて製品を選びましょう。設置目的を明確にして、補助金や助成金の活用を検討するのもおすすめです。
信頼できる専門業者に依頼すると、失敗のリスクを減らせます。自分のニーズに合った選択で、快適な住環境を手に入れましょう。